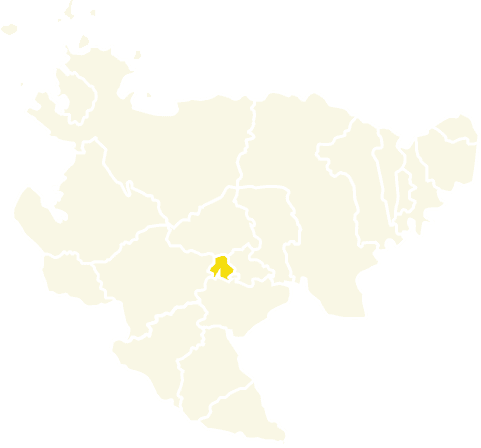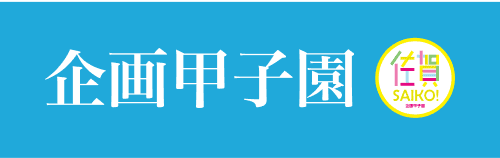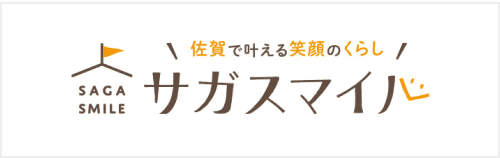佐賀県大町町の緑豊かな山すそで、「防災の専門家」として地域づくりの最前線に立つ公門寛稀さん。自動車部品メーカーの生産ラインエンジニアというキャリアを手放し、世界を巡り、被災地を駆け抜けてきました。そして今、防災をテーマに地域の人々と共に歩みを進めています。大町町を起点に、公門さんが描く「災害に強いまち」づくりは、着実に動き始めています。
公門 寛稀(くもん ひろき)さん
Public Gate合同会社代表
自動車部品メーカーのエンジニアを経て、ピースボートで世界各国を巡る。20年より大町町地域おこし協力隊(防災担当)として着任後、地域住民・行政・NPOをつなぎ、地域防災の仕組みづくりに携わる。 「六角RIVERフェス」など、地域イベントを通じた“防災・コミュニティづくり”を企画・運営。
今回、公門さんも参加された 2025年10月の伊万里市での防災実証「イタリア型避難所運営実証実験」 の様子とともに、公門さんが大切にする「防災と地域づくり」への想いをご紹介します。 この実証実験には、5日間にわたり自治体や民間企業、災害支援に関わる団体など、さまざまな立場の人たちが参加しました。
※イタリア型避難所運営とは
イタリアの避難運営体制は、市民保護局が中心となり、被災していない自治体やボランティアが連携し、標準化されたキット(TKB48:トイレ・キッチン・ベッド・48時間)で48時間以内に温かい食事、プライバシー確保のシェルター、温浴施設など質の高い避難所を被災地に展開し、被災者の尊厳と健康を守ることを目指すシステムです。被災自治体職員は被災者視点に立ち運営から外れ、被災地外からの支援者が設営・運営に当たることが特徴です。

世界を見て気づいた“日本の良さ”、そして、災害支援との運命的な出会い
—地域防災、地域コミュニティ作りの道に進むことになったきっかけを教えてください。
実家は鉄工所を営む町工場で、家業を継ぐことを意識して工業系の進路を選び、高校卒業後は自動車部品メーカーに就職して愛知県へ移りました。生産ラインをつくるエンジニアとして6年ほど働く中で、中国出向など海外での生活を経験し、自然と海外への興味が広がっていきました。
ちょうどその頃、兄が家業に入ることが決まり、「自分の帰る場所はもうないのかもしれない」と感じてしまい、工業の道を続ける理由を見いだせなくなってしまいました。24歳の時に立ち止まり、人生を見つめ直す決心をします。そして海外への関心も後押しとなり、25歳で会社を辞め、世界一周クルーズ「ピースボート」に乗船しました。これが大きな転機となります。
世界一周では、約3カ月で20カ国以上を訪れました。佐賀と愛知の狭い範囲しか知らなかった私にとって、現地で触れた社会課題、文化、風土はどれも衝撃的でした。物乞いをする幼い子ども、宗教対立、働き方や価値観の違い――。日本とはまったく異なる世界に触れ、「自分は世界のことはもちろん、日本のことも何も知らなかった」と痛感しました。
同時に、世界を知ったからこそ「やっぱり日本が好きだ」と思え、帰国後は社会のために何か役に立つ仕事がしたいと考えるようになりました。それが26歳の頃ですね。

帰国して間もなく熊本地震が発生し、お世話になっていたピースボートの災害支援団体がボランティアを募集していることを知りました。地元・九州のために何かしたいという思いから現地へ向かったのが、災害支援との最初の関わりですね。
当時、手元にあった貯金はわずか2万円。「1カ月くらいしかいられないかも……」と思いながら避難所での炊き出し支援に参加したところ、現地責任者から「長くいられるなら残ってほしい」と声をかけられました。資金の問題を伝えると、「雇用スタッフとして働けばいい」と言われ、軽い気持ちで受けたその一言が、振り返れば人生の大きな分岐点でした(笑)。
ボランティアやスタッフ、被災者との交流を通じて、人と人がつながる現場の面白さに強く惹かれ、その後は正式にスタッフとなり、熊本以降も毎年、全国の地震や水害の支援に携わるようになりました。
—全国の被災地を飛び回る中で佐賀に戻るきっかけは、なんだったんですか。
2019年の令和元年佐賀豪雨では、大町町や武雄市が大きな被害を受け、私はNPO職員として両エリアの支援に入りました。佐賀県民でありながら大町町を知らず、「どんな町なんだろう」と思いながら向かったのが最初のご縁です。
その後、佐賀での対応を終えて東北での水害支援に携わり、最終的には福島県いわき市で活動しました。しかしその頃、体調を崩したこともあり、一度NPOを離れ、普通の生活に戻ることを考えていました。
そんなタイミングで、大町町が地域おこし協力隊の「防災担当」を募集していることを知ります。地域防災に関わりたい思いがあり応募。2020年から協力隊として災害対応や地域の防災活動に取り組み始めました。着任1年目には令和3年佐賀豪雨が発生し、行政の一員として、NPOと行政の橋渡しをしながら支援に奔走したことが、現在につながる大きな経験となりました。


—地域防災、コミュニティ作りに関わるきっかけを教えてください。
現在は Public Gate合同会社 を立ち上げ、地域防災、地域振興、地域おこし協力隊の伴走支援などに取り組んでいます。災害対応だけでは事業化が難しい側面もあり、「地域防災はコミュニティづくり」という考えのもと、地域の活性化につながる事業にも幅広く関わっています。地域の力が高まれば、防災力も自然と高まるからです。
全国の被災地支援を経験する中で、家屋の復旧、制度説明、避難所対応、物資管理など、どこでも同じ支援が繰り返されている現状に疑問を持つようになりました。東日本大震災以降、毎年のように災害が起きているにもかかわらず、なぜノウハウが地域に蓄積されないのか。いつまで外部支援者が同じ支援を続けるのか。そんな問題意識が強まりました。
外部支援は必要ですが、限界があります。本来は地域の人が主体的に備え、対応できることが重要です。日本には約1700の市町村がありますが、それぞれが強くならなければ根本的な解決にはなりません。まずはその「1700分の1」である大町町を強くすることから始めようと考え、今は大町町を起点に佐賀県全体の防災力向上に取り組んでいます。

文化と祭りが支える、地域コミュニティの強さと防災力
—確かに、一つでも地域が強くなれば、隣町が被災した時に町同士で支え合うこともできますよね。先日のイベントで紹介されていたイタリア型避難所運営の取り組みも、まさに相互支援の仕組みでしたよね。
現在の日本では「市町単位で支援する」仕組みになっており、広域連携の枠組みが十分ではありません。一方イタリアでは、近隣自治体が自然と助け合う広域支援が制度として機能しています。そうした仕組みは日本でも必要だと感じています。
ただ、日本では日常的に災害支援に触れる機会は少なく、協力がなければ成り立たないのに、実際に動く機会も多くありません。本来は災害が起こらず、僕らのような支援者がいない方がいい世界ですが、日常では必要性を認知されにくく、災害発生時には求められる場面もあるという矛盾を抱えています。
「防災をしよう」と発信しても、受け取らないまま災害が起き、被災当事者になってしまう人も多く、その難しさもあります。さらに、地方では少子高齢化が進み、地域運営そのものが厳しくなる中で防災体制を整えるのは簡単ではありません。とはいえ、限界はあっても「やるべきことはやる」。その現実と理想の間で、防災がなかなか進まない日本社会の課題を強く感じています。

—先日、唐津くんちを拝見したのですが、町ごとで縦、横のつながりがしっかりしているのを感じました。各町の一体感が非常に強く、「公門さんが取り組んでいることって、こういう“地域のつながり”をつくることなんだな」と思ったんです。
その通りです。「祭りのある地域は強い」とよく言われます。伝統文化や祭りは、住民同士が一致団結する場であり、普段関わりの薄い人同士でも、祭りの仲間として自然に支え合う関係が生まれます。こうしたつながりがある地域では、災害など“いざという時”にも助け合いが起こりやすいんです。
しかし、人口減少とともに全国的に祭りや文化の規模が縮小し、コミュニティの力が弱まっている地域も増えています。都会でよく言われる「隣の家の人を知らない」という状態は、災害時には孤立や孤独死のリスクを高めます。横のつながりがないこと自体が、最大のリスクになるのです。
だからこそ、祭りのように地域の人が日常的に交わり、声を掛け合う仕組みがあることは、そのまま“防災力の高さ”につながります。また、防災の形は地域ごとに異なるため、外部からの「こうするべき」という考えが必ずしも当てはまるわけではありません。最もよく知っているのは地域の人たち自身で、彼らが主体的に考え、行動できる状態が理想です。その意味でも、祭りのように地域全体が一体となる文化を残し、継続することは、地域防災にとって大きな力になります。

六角RIVERフェスにみる、民間でつくる新しい“流域コミュニティ”
—そういう意味で、コミュニティづくりの一つの形として「六角RIVERフェス」などの地域イベントの運営・開催につながってくるんですね?
唐津の「唐津くんち」のように、定期的にフェスを開催し、その地域ならではのコミュニティをつくることを狙いとしています。今年は江北町の人たちが中心となって、「六角RIVERフェス」を開催しました。
このフェスは、地域の人たちが主体となって企画・運営するスタイルなので、毎年内容や雰囲気が少しずつ変わります。ただし、「六角川をテーマに、地域をまたいで一緒に考える」という軸は変わりません。六角川流域のコミュニティが横につながる場をつくることが目的です。
六角川は佐賀市、武雄市、小城市、白石町、大町町、江北町の三市三町を結んでいます。しかし、行政区域を超えると横のつながりは急に薄くなるのが現状です。流域で起きる災害の多くは水害であり、流域全体で協力して備えることが不可欠です。こうした想いが、フェスを始めるきっかけとなりました。
また、行政任せにはしたくなかったため、昨年はほぼ民間主導で実施。地域企業には協賛として支援をいただき、地域の人々にもボランティアとして多く関わってもらいました。中心メンバーの知り合いを巻き込み運営体制をつくるなど、人のつながりを生かしながら、地域主体のフェスとして育てています。

写真提供:公門 寛稀さん
—まだこれからの部分も多いとは思いますが、実際にやってみて、手応えはいかがでしたか?
良かった点と課題の両方がありますが、まず大きかったのは “民間主体でやった” ことの効果です。そのおかげで企業の方々が「応援するよ」と言ってくださり、想像以上に協賛が集まりました。地域の方々の協力もとても大きかったです。
また、大町町に移住してきた人や、町外に住みながらも大町に関わってくれる人など、立場の違う多くの人が同じ思いを持って一つのイベントをつくり上げました。そのプロセスが “共同” を生み、地域の連携がより強まったと感じています。これは大町町にとって大きな財産になったと思います。
さらに、参加者や出展者、ステージ出演者など、関わった皆さんが「とても良いイベントだった」と口をそろえて評価してくれました。関わった人たち全員が“三方よし”で喜んでくれたイベントになったことは、本当に良かった点だと思っています。
開催後もイベントを通して知り合った白石の方や、「六角RIVERフェス」のデザインを担当してくれた方たちと、大町町のイルミネーションを一緒につくるなど、新しい協働が生まれました。すべての人が同じように動けるわけではありませんが、少しずつ横のつながりが広がっているのを感じています。また、地元の方々にも「大町で何かをやっている人」として認知してもらえるようになり、活動がしやすくなったと感じています。
とはいえ、新しい取り組みを始めるたびに、「まだまだだな」と感じる場面は多くあります。活動を知らない人から「誰だ?」と言われたり、「そんなイベント知らない」と言われたりすることもあります。防災ドローンの取り組みでは、よく分からない活動だと思われて誤解されることもあり、「怪しい」と言われたことも。まだまだ理解や認知が足りず、課題は多いですね。

地域で活動する難しさは “人” ──だからこそ面白い!
—地域コミュニティの強化や防災活動を進めていく中で、一番の難しさは何ですか?
やはり、一番の難しさは「人」ですね。小さな地域では、一度何かあると関係が続かなくなることもあり、常に相手への気遣いが必要です。協力をお願いした以上、自分も相手に返さなければならず、つながりが増えるほど頼まれごとも増え、自分の時間もどんどん減っていきます。こうした「人間関係の大変さ」は、地域ならではの難しさだと感じています。
その一方で、僕自身は「地域のために」ということを意識しすぎないようにしています。自分がやりたいから取り組んでいるので、その結果として誰かの役に立てれば十分だと考えています。自然災害は避けられませんが、住む場所を選んだ以上、基本的には“自己責任の範囲”もあります。それを突き放すのではなく、困っている人を助ける仕組みや、行政だけでは届かない部分を民間で補う仕組みが必要だと思っています。
令和3年の豪雨の際には、日頃から地域とのつながりを作っておいたことで助け合いが生まれました。備えた分だけ返ってくる実感もあります。やらなくてもいいけれど、僕は「やりたいからやっている」。どんな形で返ってくるかは分かりませんが、今後も続けていきたいと思っています。

—“やりたいからやっている”という価値観の中で、やりがいはどこにあるのでしょうか?
正直、「やりがい」という言葉で整理するとしっくりきませんが、強いて言えばいくつかあります。
まず、誰もやっていないことに取り組む面白さがあります。災害現場を経験する中で、根本的な課題に向き合える機会はそう多くありません。だからこそ、自分のアイデア次第で物事が動いたり、思いがけない方向に進んだりするのが面白いのです。
そして何より、地域の人と仲良くなれることが大きい。大町町に残ろうと思ったのも、災害時に地域の人が温かく受け入れてくれたことがきっかけでした。活動を続ける中で応援してくれる人が増え、協力してくれる人がいる。その温かさが、自分を支えてくれていると感じます。
地域コミュニティに深く入ることで、人間関係や歴史、文化など“地域のリアル”も見えてきます。大町町は31地区ありますが、地区同士の関係性や個人の相性など、人間模様も自然とわかるようになります。地域性や歴史をひも解くことで、「この地域に合った防災とは何か」を立体的に考えられるようになるのです。そういう意味でも、防災は多角的に関わることができる“面白いテーマ”だと思います。
人口戦略会議の報告書によると、佐賀県内では2020年から2050年までの30年間に、20~39歳の若年女性人口が半分以下に減少すると推計され、「消滅の可能性がある」とされた自治体は、多久市、玄海町、大町町、白石町、太良町の5市町です。大町町も含まれていますのでこれからの街づくりには大きな課題もあります。それを“仕事にする”のは簡単ではありませんが、考え続けたい領域です。さらに、同じ領域で活動するライバルがいないため、自由に挑戦できるという面もあり、大町町には、ライバルがいないからこそ「動いたもの勝ち」で、先駆者として挑戦できる環境があります。
佐賀県の中でも、“大町町という資源が少ない場所に突然現れた存在” として、僕自身が逆に地域に引っ張ってもらえている部分もあると思います。結局、大変なことも多いけれど、面白いからやっている。それだけなんです。

3〜5年後の展望 ──「防災といえば大町町」と言われるまで
—3年〜5年ほどの近い将来で、実現したいことや展望はありますか?
ずっと考えているのは、「大町町を佐賀県で一番、災害対策に強い街として認知される存在にすること」です。3年後か5年後かは正確にはわかりませんが、県内の自治体や関係者が「大町町の取り組みを参考にしたい」と思うような仕組みや地域づくりを目指しています。「防災といえば大町町」と言われるような町にしたい。それが今の大きな目標です。
大町町には特別に強い産業や観光資源があるわけではありません。だからこそ、災害を負の経験で終わらせず、“経験したからこそ備えが進んだ町”として、安心して暮らせる町をつくりたいと考えています。人口が増えればもちろん嬉しいですが、「災害があるから住みにくい」という印象を持たれない町でありたいと思っています。
将来、自治体のあり方が見直されるような局面が訪れることも考えられます。そのときに、「大町町は災害対策にしっかり取り組んでいる」「災害に強い地域としての確かな特徴がある」と自然に評価される存在でありたいと思っています。どこかに埋もれてしまうのではなく、大町町ならではの個性と強みを大切にしながら、対等な立場で議論や連携に臨める町でありたいと考えています。
観光や特産品で勝負しても、強みがない部分では正直勝てません。だからこそ、ないものを求めるのではなく、いまあるものを最大限活かすことが大事だと思っています。そのために、地元の人やお店を営む人、意欲ある移住者、大町町を盛り上げたいと思う人たち、そうした“やる気のある人たち”が同じ方向を向いて動けるようにしていきたいです。みんなで“小さな大町”を一緒に盛り上げていく。そんな町づくりを目指しています。

—地域を盛り上げようとしている若い人たちへのアドバイスをお願いします。
難しい質問ですね(笑)。ひと言でいうなら「若いうちにたくさん苦労しておいた方がいい」ということです。さまざまな嫌なことや理不尽なことを経験しておくと、30歳を過ぎたあたりから物事を割り切れるようになります。「まあ、そんなこともあるよね」と思えるようになり、自分らしさも出しやすくなるんです。
僕自身も、厳しいサラリーマン時代を経て海外を見て、NPOで叩き上げられた経験があります。見た目はヘラヘラしていますが、結構頑張ってきたつもりです(笑)。そうした “いろんな世界に触れた経験” が、今の自分を支えてくれていると感じます。
だから若い人には、自分の幅を広げるような経験をできるだけたくさんしてほしいと思います。それが結果的に地域への還元につながるはずです。別に、まちづくりに直接関わる必要はありません。自分がやりたい場所で、自分ができる形で、何かしら協力できることを実行すればいい。そうした経験が、どこかで地域の力になっていくはずです。
無理に「地域のために」と考えなくてもいいんです。まずは自分の軸をつくること、そしてそのための経験値を積むこと。それが一番の近道なんじゃないかと思います。