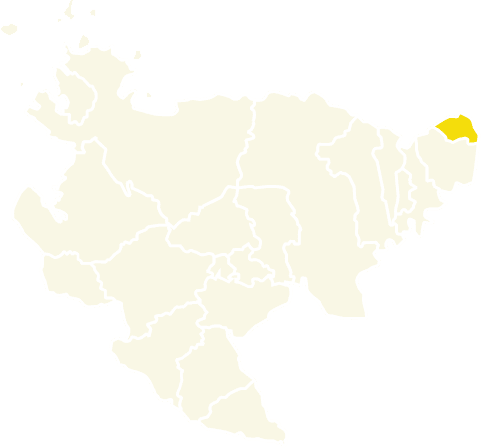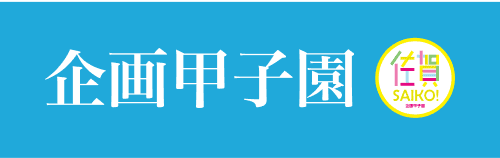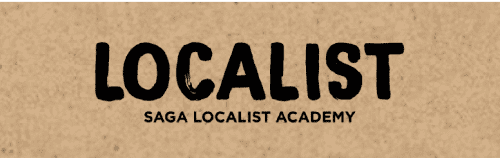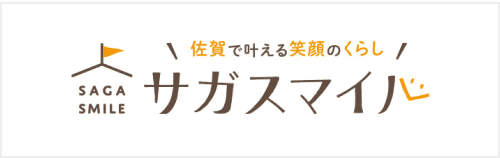基山町の園田地区で活動しているNPO法人かいろう基山さんは、中山間地域の全国共通の課題である竹林問題を解決すべく日々活動をおこなっています。
活動の様子を取材しました!


里山を再び財産に
かつては、タケノコやメンマとしての「食材」で、さらに「器」や「建材」にと、利用価値が高いからからこそ人は竹林と共存した暮らしがありました。
しかし現代の生活様式の中で竹の利用は年々減っています。さらには利点のひとつであった育ちの早さがネックとなり、各地で竹害として悩みの種となってしまいました。
かいろう基山さんでは、そんな竹害と戦うのではなく、再び竹を財産に変えていくため地域で里山保全の仕組み作りを続けています。

もともとは自衛隊OBの方々で始まった団体とのこと。事前にお聞きしていた年齢を感じさせず、びっくりするほどのご健脚です。現場での打ち合わせの後、道具を手にすっと山の中に消えていきます。しばらくしたら、「倒すよー」「おーらい」と幾度かの声掛けが響いたあと、竹がバサバサっと倒れてきます。

作業は手慣れたもので、竹を切り倒してからあっという間に小分けにされて、道沿いに積み上げられていきます。毎年1000本ほどを切り倒し、その一部を製品に用いて活用しているとのこと。2004年1月の発足から継続的なボランティア活動を経て、現在約5.6haの面積の山林の手入れを行っています。

無理がないから続けられる
1時間ほど作業したら、「よし!そろそろか!」と、誰ともなく声があがり各々のタイミングで作業を終えられます。無理なく、長く続けられる形を模索して、現在は火曜日から土曜日の8時30分~11時30分が主な活動時間だそう。
各々が参加出来るときに活動を楽しみながら関わっているとの事でした。活動の様子はこまめにSNSなどで共有されています。

山の中で竹を切り倒すだけではなく、下山してからも沢山の作業があるとのこと。
竹を乾燥させるため資材倉庫の上に重ねたり、子どもたちと楽しむための竹飯盒や流しそうめん用の竹の加工を行ったり、竹炭製品をつくるために小割したり面取りを行ったりと様々です。
当日の天気に、参加人数、それぞれが持つ技術や体調、年間スケジュール、目的にあわせて多彩な活動が展開されています。
かつてといまの共存
その活動のどれもが、中山間地で暮らすうえでかつて行われてきた営みの再現に見えます。
一方でかつての暮らしの中にあった竹の使い方だけではなく、機械で粉末にして土壌改良材として活用するなど、現代の技術や流通システムに組み込んだ新しい竹の活用も行っています。

例えば現在、主力商品となっている「基山の力」は竹チップが持つ分解能力を、畜産の世界で良質の牛床材として活用した後回収し、さらに農業で用いる土壌改良材や、家庭で発生する生ごみの削減用にコンポストの基材として活用されています。

この活動に基山町も連動し、「基山の力」は基山町在住者による購入に対して半額を補助するという独自の支援も始まっています。中山間地の困りごとを解決しながら、まちのゴミ削減策の提案事業にもつながり、地域全体の取り組みとして発展しています。
基山の力
https://www.town.kiyama.lg.jp/kankou/kiji0035850/index.html
かつては当たり前にあったが、忘れてしまっていた森と人の暮らしの循環や、地域社会と森との共生を現代の仕組みで、少しずつ取り戻す仕掛けにも見えます。
山暮らしの知恵と試行錯誤の楽しさ
かいろう基山さんの活動は、山あいで暮らす技、山の恵みを楽しむ知恵などを実践し、教えていただきながら知識を得る事ができる場にもなっています。都市部を離れ山あいや里山に移住をしてみたい、暮らしてみたいという希望者や、Uターンして戻ったけれど、若くして故郷を離れたため山暮らしを知らない方など、様々な方が山暮らしを学ばれています。
かいろう基山の5代目代表である松原さんに、会員以外の参加も大丈夫なのかお尋ねすると「今まで以上に積極的に参加者や視察を募集しています」とのことです。
里山保全活動において伐採した竹を竹製品に資源化し、竹の循環システムを目指す取り組み | @佐賀県 三養基郡基山町 | Shisaly (シサリー)
https://www.shisaly.com/plan/4524
この取材をしている最中にも、年に数回しか行わない「竹炭づくり」に誘われました。
竹炭づくりは、数か月かけて自然乾燥させ形を揃えた竹を窯に詰め込み、火入れします。

窯から上がる煙の量や色を見ながら、中の様子を説明していただきました。何度焼いても同じにならず、出来上がった竹炭の良品は20%前後とのこと。難易度が高く、奥が深い炭焼きの面白さが伝わってきます。
繰り返し、工夫する
丁寧に火入れからの窯内部の温度変化の記録を取りながら、試行錯誤の連続だそうです。広葉樹よりもずっと燃えやすい竹を、高品質の竹炭にするというのは相当な技術が必要とのことでした。

かいろう基山で体験できる数々の作業や、参加する方々の面白さに惹かれ、最近通い始め竹炭製品の生産を担当している新会員の服部さんも楽しそうです。沢山の方と、山の事、地域の事を語り合いながら、煙の揺らぎを眺めゆっくりとした時間のなかで作業が進みます。
日が沈み、耳を澄ませば隣を流れる沢の音に火のはぜる音が混じりました。山麓で源流を感じながら丁寧な暮らしというものを考えます。窯内部の様子を想像し、煙と音、温度計の数字を見ながら空気を遮断するタイミングを見極めます。作業時間自体が癒しの時間なのかもしれません。

温度が下がるまで数日まって、いよいよ窯出し。竹の伐りだしからしたら約3か月にわたる時間の流れの中で作られた竹炭です。

出来上がりの炭も各種商品に求められる品質に合わせて仕分けます。家庭でよりおいしくご飯を炊くための炭のほか、農業資材の土壌改良材、建築資材の湿度管理材など、多彩な用途で販売されています。
かいろう基山オリジナル商品 – かいろう基山
https://kairoukiyama.jimdofree.com/new-%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B

住居跡地が長年放置され竹林になってしまった場所を、定期的に伐採し竹林の拡大を食い止めることに成功したとのこと。
その後植林を行いとても大きな木が育っていました。木の太さから竹防護活動の継続年数の長さを感じます。そして、かいろう基山の会員さんはさらに先を見ています。「これからこの土地を、皆の遊び場にするんだ」とワクワクした目で教えて頂いたのは、長年活動に参加している会員の鶴﨑さんです。

世代を超えて放置山林を里山として取り戻していく。会員さんや、参加者の皆さんと共に、竹林整備で風通しが良くなった森を、地域を学び楽しむ場所に作り変えていきたい、とのこと。
炭焼きの火の前で参加者で話し合った内容を描いたイメージ図(初案)のことを、あれこれ話す時間はとても贅沢な時間でした。