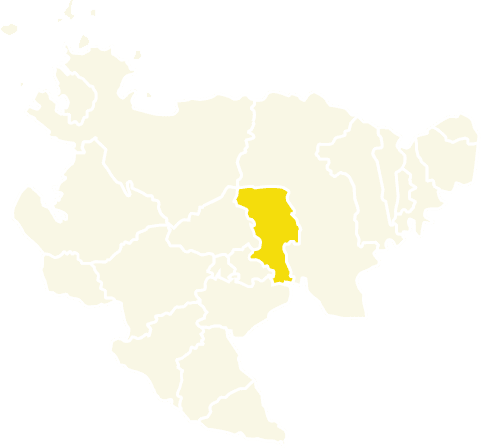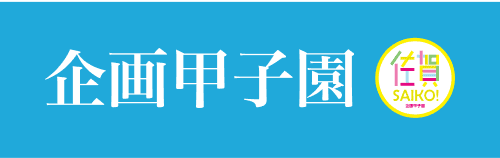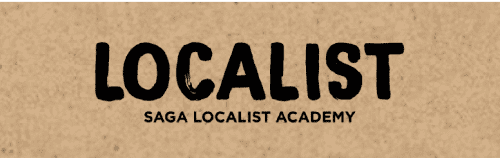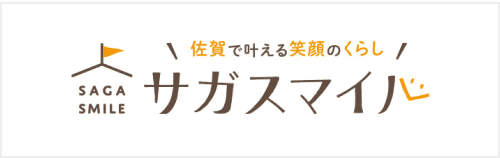小城市で造園業を営む久我稔さん。2023年のイベント「ARKS星あかり」の企画運営や中山間地の活用を目的とするアオモジの栽培、青文字茶(あおもじちゃ)の製造など、造園以外のことも精力的に取り組んでいます。なんといずれはブドウ栽培とワインづくりにも挑戦してみたいそう!バイタリティあふれる久我さんのモチベーションとさまざまな取り組みについて詳しく伺いました。
久我稔さん
植木屋花みどり代表
高校卒業までを小城市で過ごした後、他県への進学・就職を経て20代半ばでUターン。その後、造園の道に進む。現在は「植木屋花みどり」の代表として個人宅の庭や小城市内の公園などの造園を手がけるほか、中山間地の活用や「ARKS星あかり」などのイベントにも携わっている。
https://sites.google.com/uekiyahanamidori.com/midori/ホーム?authuser=0
造園からお茶づくりまでやりたいことはなんでもやる
—他県での就職を経て20代半ばで小城にUターンし、造園業に就いたきっかけはなんでしたか。
高校卒業後は写真の勉強をしたり、いくつか仕事を経験したりして、24歳ぐらいの時に小城に帰ってきました。昔の仲間から「向いているんじゃないか」と言われたこと、もともと木に関わる仕事がしたかったこと、職業訓練で「この人には一生ついていけるな」と感じた職人さんとの出会いがあったことで、職人さんの元で造園の修行を始めました。

今は個人の庭の管理や造園のほかに、小城公園や牛津の肥前仏舎利塔の管理、植木の販売もしています。造園、と一口に言っても木を植える、剪定する、伐る、石を積む、草をむしるなどいろんな作業があります。自分が時間と技術をかけて結果が変わる仕事をしたかったので自分に合っているなと思います。

—庭づくりのやりがいをどのようなところに感じますか。
人間を育てる要素として「庭」は家の中でとても大事なポジションだと思います。家に住んでいる人にとって庭がコミュニケーションの場になっていると、家は良い環境になっていくし、家族も幸せに生活できる。そういう面では人に対してある程度貢献できているのかなと。
—数年前から中山間地の活用にも力を入れているそうですね。具体的にどのようなことをされていますか。
自分の作業場周辺の山は、元々ミカンを栽培していたところが多いんです。でも、代替わりしたり、高齢化したりして、傾斜が強いエリアからどんどん辞めて藪になって、他の野生動物との境界線が下がっていっているのが問題になっていました。里山の保全にかかわる仕事をしたい気持ちは長年ずっとあったので、そういった土地に「アオモジ」(※)を植えて、その葉っぱから青文字茶(あおもじちゃ)を作ることにしたんです。
※アオモジ…クスノキ科に分類される落葉小高木の一種。青文字茶にはビタミンやミネラル、抗酸化成分が含まれており、健康や美容に効果があると言われている。

—さまざまな植物がある中で、なぜアオモジだったのでしょうか。
知り合いからアオモジはとても体に良いし、佐賀や長崎は自生率が高いと聞いて「これは作らないわけにはいかないだろう」と思いました。でも忙しいからとしばらくほったらかしにしていたんですよね。その後、知り合いや親せきが立て続けに病気で亡くなって、できることがあるのに何もしない自分が情けなく思えたんです。それで2022年からアオモジの栽培や青文字茶の製造・販売に取り組むことにしました。
—使命感を駆り立てられることが次々と起きたんですね。山に植物を栽培して人の手を定期的に入れるだけでも害獣被害などの防止になるんでしょうか。
人間と野生動物の「ボーダーライン」をちゃんと作ってあげることが大事なんですよ。昔は、ミカンなどの果樹を植えた先にカシの木とか炭にできる樹木を植えて、「ここまで人間が入ってきますよ」ということを示していたんですよね。それが里山なんだけど今はその環境が一度崩れてしまったのでやり直しているところです。

アオモジの栽培や青文字茶の販売は小城商工会議所から『小城の輝き!良か事業所表彰事業』として評価いただきました。地域に貢献できているのかなと思います。
ゆくゆくは、ブドウ栽培に切り替えてワインを作るのが野望です。
—そうなんですね!?後ほどくわしく教えてください。

自分のためだけに生きるのは全然おもしろくない
—2023年度は佐賀市の「くすかぜ広場 ARKS」で、竹でつくった照明“ほしあかり”を灯すイベント「ARKS星あかり」の企画運営もされていましたね。

約630本の佐賀県産の竹を使って照明を制作しました。普段、夜空を見上げることってそんなにないと思うんですけど、竹を組み立ててドームのようなものを作ったり、竹を丸く編んでボールのようにしたり、いろんな形の照明を設置したら、夜空がとても高く見えるようになりました。
若いお客さんにもたくさん集まっていただいて、子どもがドームの中に入って遊んでいるのを見て、おもしろいものができたなと思いました。普段の造園業では関わらない人たちとも関われたのは良かったですね。
—本業の造園業もお忙しいですし、人を雇用して会社を経営していくのも大変な部分があると思います。それでも、中山間地の活用やARKS星あかりなどの活動に精力的に取り組んでいらっしゃるのはなぜですか。
仕事自体がそういうものなのかなと。自分の生業をしてお金をもうけて、家族に飯を食わせればそれでいい、ではなくて、結局いろんな関係性の中で自分は成長するし、周りも一緒にいろんなことに挑戦できる。自分の事業の枠から出ません、となると何もできないし、新しいものも生まれない。やっぱり挑戦したいっていう思いがあるからでしょうね。
最近は、プライベート、仕事、将来のため、自分のためとか全部ごっちゃになって、境界線がないから、逆に言えば仕事も仕事と思ってないんやろうね。ただ単に人のために何をするかを考えて生きているだけだから。結局、自分のためだけに行動するのはたまらなくおもしろくないんじゃないかな。
24歳でUターンしてきた時、地域で通用する人間になってはじめて世界で通用する人間になるんだなと自覚したんですね。だから、地域に根ざした活動をして地域に求められる人材にならんといかんねと思って小城に帰ってきたときの気持ちはずっとあります。

小さくても循環する社会の象徴としての“ワインづくり”
—ゆくゆくは中山間地でブドウを栽培してワイナリーをしたいとのことですが、どういう思いがありますか。
昔からワインが好きなんですよね。小城にUターンする前、キャンティワインをずっと飲んでいたら抽選で旅行券が当たったからイタリアのキャンティ(ワインの産地として有名な地域)に行ったんです(笑)キャンティのワイン畑を見て「これはいつか自分がふるさとでやらないといけないことかもな」と漠然と思ったんですね。佐賀だと仲間内の集まりでワインを飲む機会はあまりないんだけど、お酒はやはり人をつなげてくれるんだと思うことはたくさんあります。
小さい規模でも循環している社会はいいなという思いもあります。ワイン作りを実現できたら中山間地の活用、地域の特産品の生産、そして自分の個人的な野望と3つのことが達成できるし、地域の循環に貢献できる。ワインが好きだから自分で作ってみたいし、それで人の役に立てたらなお良いなと思っています。
—精力的に活動しながらも地域や自分の活動を俯瞰的に見ている印象です。
造園の仕事をしているからか調和を意識することが多いんです。切り損ねたら思わず木にごめんって言ってしまうし、木の上に登って作業をしている時に体重をかけすぎたらやはりごめん!となるし、ぐじぐじ伐ってたらかわいそうになる。伐るならスパッと一発で伐ってやるぜみたいな気持ちになってくる。
そういう感覚だから人の輪、地域の輪がぐるぐる回っているのを見ていたいのかな。ワインでそれができたらいいなと思っています。

いま息子が他県にいますが、いつかは佐賀に戻りたいと言っているので、帰ってきたら一緒にワイン作りをしようと約束しています。